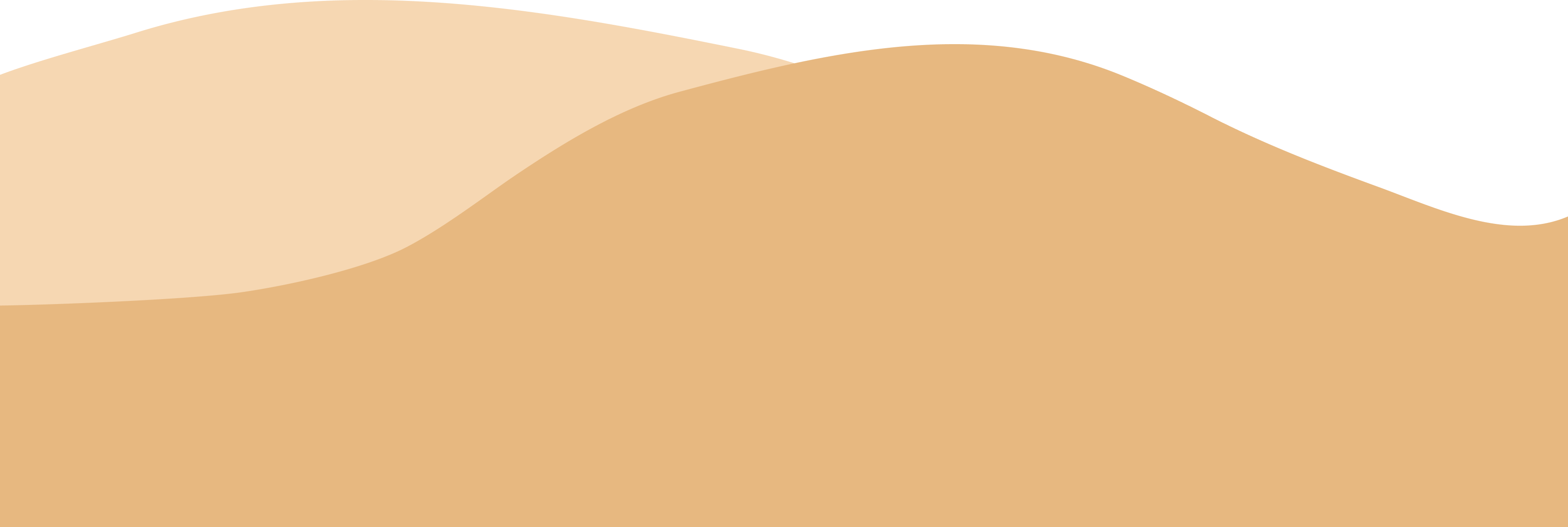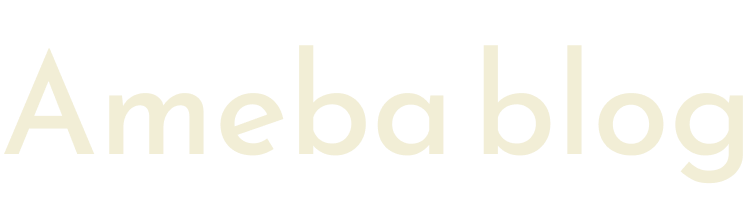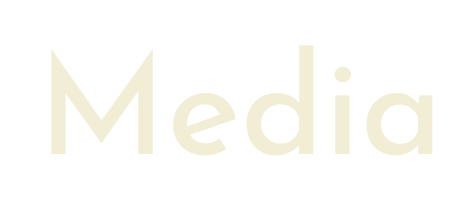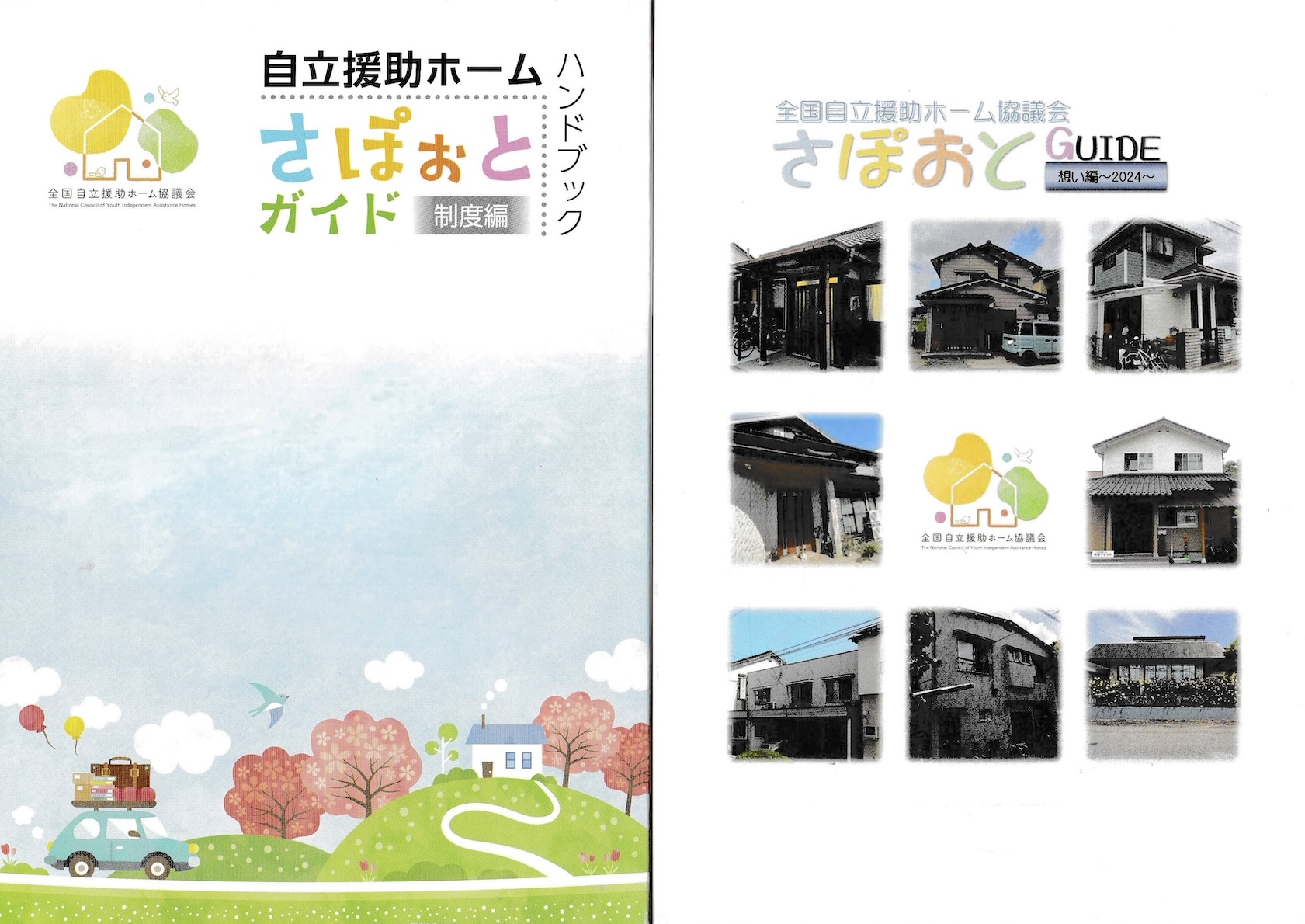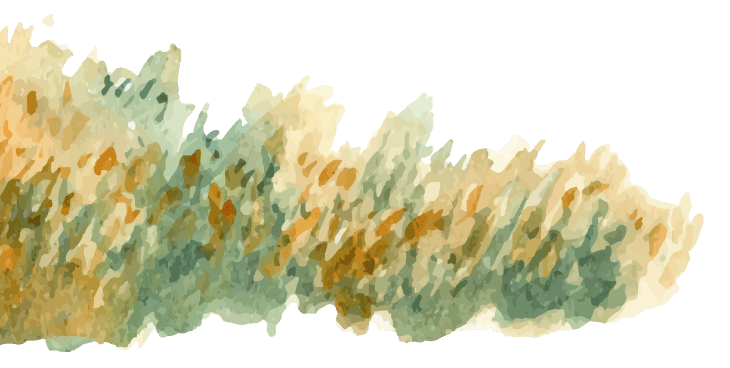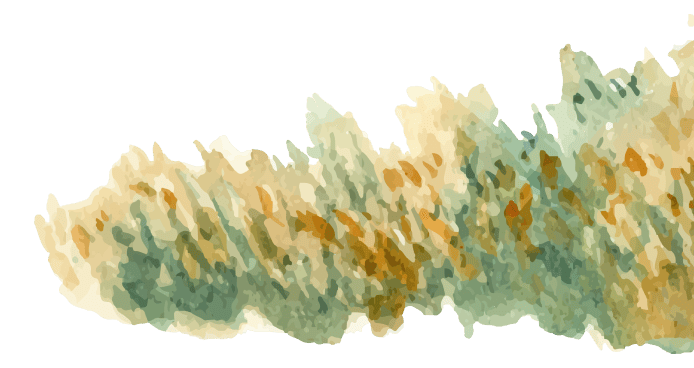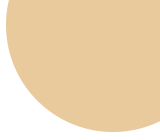

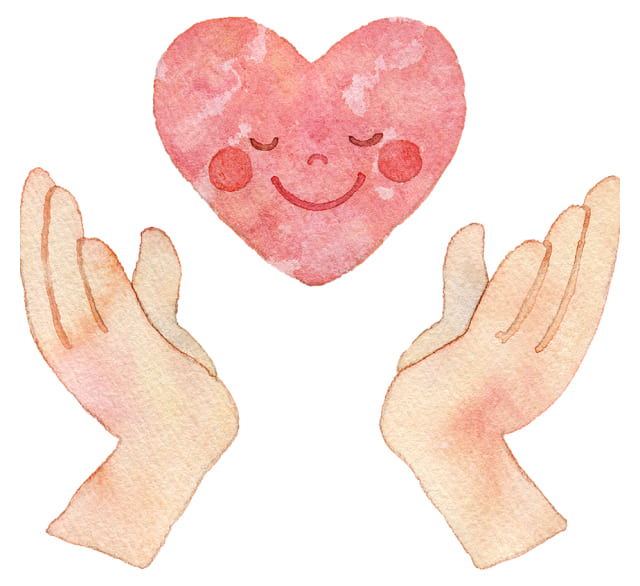
マナーズはこどもたちの“第二の家族”としてめいっぱいの愛情を注ぎます。
マナーズはこどもたちの“第二の家族”としてめいっぱいの愛情を注ぎます。
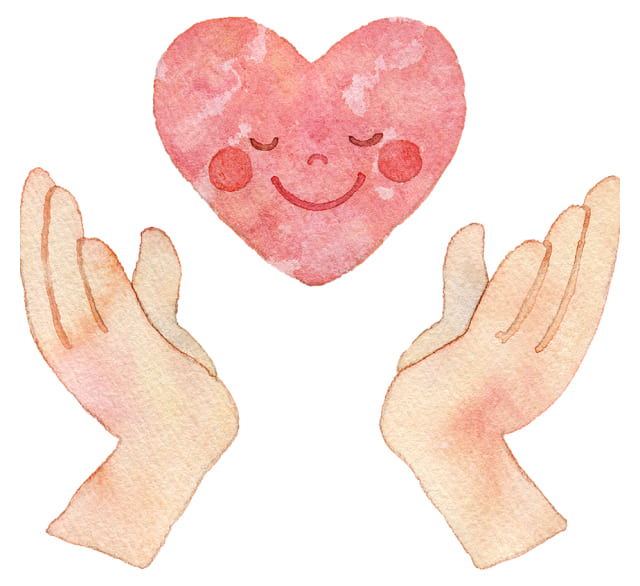
こどもは、愛される経験をすることで人を愛することを学び、安心して過ごせる場を持つことで社会に飛び立つ勇気を得ます。
「あなたは、愛されている存在なんだよ」――わたしたちマナーズは、自立援助ホームとこども食堂の運営を通して、すべてのこどもたちにこのメッセージを伝えつづけます。

自立援助ホーム
家庭での居場所をなくしたこどもと共に暮らし、社会で自立生活を送る準備をサポートします。マナーズは茨城県つくば市で、男子用ホーム「ハレルヤ・ファミリー」、女子用ホーム「グレイス・ファミリー」を運営しています。
こども食堂
親子を含めた地域の人々に、安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供する取り組みです。マナーズは毎月第1・第3水曜日の夕方、つくば市北中妻にあるレストラン跡地で“つくば「こどもの家」食堂”を開いています。